実験の目的
機能と設計結果の確認を行います。
差動増幅回路にはいくつかのバリエーションがありますが、今回の実験では
定電流源は使わず抵抗器(RE)とします。
実験課題
- 直流動作点
- 波形確認
- 差動利得
- 同相利得
- CMRR
実験回路
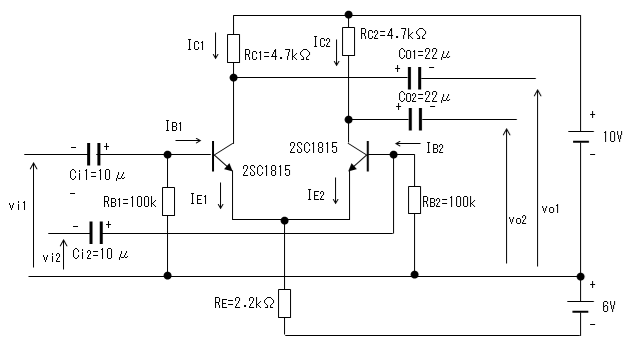
回路の動作
出力もふたつ(vo1、vo2)ありますが、ふたつの出力は同じ波形で位相が
180°ずれています。出力は必ずしも両方使う必要はありません。
ふたつあるトランジスタのエミッタ端子は共通になっています。
抵抗REは定電流源にする方が性能がよくなりますが、今回は抵抗のままで実験します。
電源はプラスマイナスの電源にした方が、バイアス回路が簡単になるので、電池を使用して
マイナス側電源としました。このためプラス側とマイナス側とで電源電圧が異なりますが
その前提でバイアス設計すれば支障はありません。
差動増幅回路の詳細な動作はこちらを参照してください。
実験回路の設計
- 設計条件 (1)使用するトランジスターはTr1、Tr2とも2SC1815のYランク。
- バイアス回路の設計
- RB1、RB2の選定 トランジスターは2SC1815のYランクなのでデータシートよりhfeは120〜240
- REの選定 トランジスタのベース〜エミッタ間電圧(VBE)を約0.6[V]とすれば
- RC1、RC2の選定 トランジスタのエミッタの電位は対グランドでみると約−1.2[V]です。
- 増幅回路の等価回路
- 電圧増幅度の計算
- 同相利得の計算
- CMRRの計算
- 出力インピーダンスの計算
- 入力インピーダンスの計算
- コンデンサの容量の決定
- 入力コンデンサ(Ci1、Ci2) CiはZiおよび信号源内部抵抗(Rs)とともにローカットフィルターを
- 出力コンデンサ(Co) 出力コンデンサー(Co)と出力インピーダンス(Zo)と負荷抵抗(ZL)は
(2)電源電圧は+10[V]、-6[V]とします。
差動増幅回路はプラス・マイナスの電源にした方がバイアス回路が簡単になります。
今回は、マイナス側のみ電池を使うこととしたので、プラス側とマイナス側で
非対称な電圧としました。
(3)コレクター電流:Ic1=Ic2=1mA
(4)電圧増幅度: 規定はしません。
が、結果的に実験回路において理論上いくらになるかを計算し、測定結果と比較します。
(5)増幅する周波数帯域の最低周波数は50Hz
(6)入力側(信号源)の出力インピーダンスは600[Ω]
(これは発振器の出力インピーダンスです)
(7)出力側(負荷)の入力インピーダンスは1[MΩ]
(これはテスターアダプターの入力インピーダンスです)
となります。コレクタ電流Icは1[mA]としたので、ベース電流IBは
IB = Ic / hfe = 1[mA] / (120〜240) ≒ 4.2〜8.3[μA]
となります。
RBとしては、通常10[kΩ]くらいでの設計を多く見かけます。
しかし今回の実験では大きめの100[kΩ]で設計してみます。
このときのRBの電圧降下は
IB * RB = 4.2〜8.3[μA] * 100[kΩ] ≒ 0.4〜0.8[V]
になりますので、結局、VB1 = VB2 = −0.4〜−0.8[V]
となります。間をとってVB1 = VB2 = −0.6[V]で 設計を進めます。
もし、RBが10[kΩ]以下ならVBは0.1[V]以下になるので
VB ≒ 0[V]で設計しても問題ないでしょう。
VEはベース電圧VB1およびVB2より
0.6[V]を引けば決まります。VEEは−6[V]でしたので
VE = VB1 - 0.6[V] - VEE = - 0.6 - 0.6 - (-6) = 4.8[V]
VE が決まればREを決められます。
RE = VE/(IE1 + IE2) ≒ VE/(IC1 + IC2) = 4.8[V]/(1[mA] + 1[mA]) = 2.4[kΩ]
E6系列より選定し RE = 2.2[kΩ]としました。
なお以上の設計より、REを定電流源に近くするためにできるだけ
大きな値にするためにはVEEを大きくする必要があることが
判ります。そして、VEEを大きくすることなく(等価的な)REを
大きくするためにはこれを定電流源にすると実現出来ますが、
今回は固定抵抗器で実験することにします。
VCC = 10[V]なので、コレクタ〜エミッタ間電圧VCEと
RC1とで半分づつ電圧を配分すると、RC1での
電圧降下は5.0〜5.5[V]くらいになるので
RC1 = 5.0[V] / Ic = 5.0 / 1[mA] = 5[kΩ]
となるので、E6系列より選定し RC1 = 4.7[kΩ]としました。
RC2も同様にRC2 = 4.7[kΩ]とします。
IE1 + IE2 = (Vcc - VBE1 - VEE) / RE = (- 0.6 - 0.6 - (- 6)) / 2200[Ω] ≒ 2.18[mA]
IE1とIE2が等しいならば
IC1 ≒ IE1 = 2.18[mA] / 2 = 1.09[mA] ≒ 1.1[mA]
RC1での電圧降下VC1は
VC1 = IC1 * RC1 = 1.1[mA] * 4700 ≒ 5.2[V]
となりました。再計算した結果を下図に纏めます。
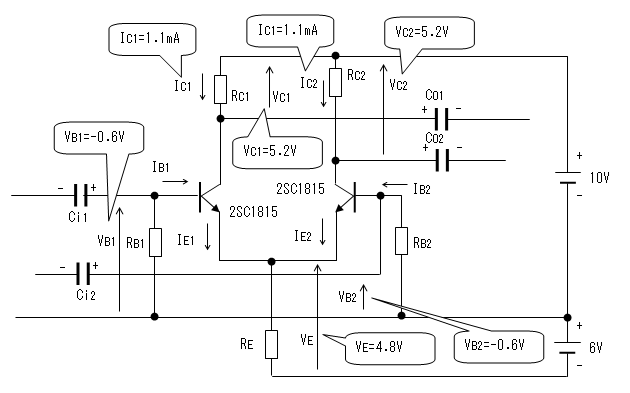
-
ふたつのトランジスタをエミッタ接地の
簡略化等価回路で置き換えます。
また、電源のVCCとVEEは理想的にはインピーダンスが0なので
交流的にはGNDに接続されるのと同じです。結局、等価回路は
下図にようになります。
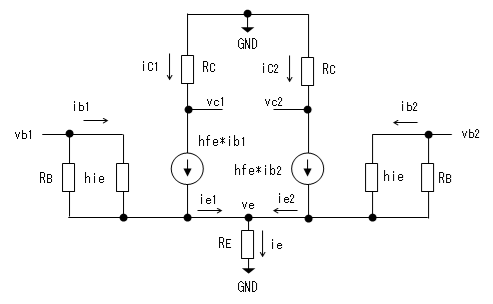
-
電圧増幅度Avは次の式で与えられます。
Av = −Rc * hfe / (2 * hie)
計算にあたってはhieの値が必要となりますが、次の概算式を使いました。
hie = β/(40 * Ic)
この式をAvの式に代入するとβはhfeのことなので
Av = −Rc * hfe / {2 * β/(40 * Ic)} = −20 * Rc * Ic
この式で電圧増幅度Avを計算すると
Av = −20 * 4700 * 1.1[mA] = −103.4
-
同相利得Acは次の式で与えられます。
Ac = Rc / (2 * RE)
この式にて計算すると
Ac = 4700 / (2 * 2200) = 1.068
-
CMRR(同相モード除去比)は次の式で与えられます。
CMRR = (2 * hfe / hie) * RE
概算式hie = β/(40 * Ic)を使うと
CMRR = {2 * hfe / β/(40 * Ic)} * RE = 80 * Ic * RE
この式にて計算すると
CMRR = 80 * 0.0011 * 2200 = 193.6
-
差動増幅回路の等価回路から出力インピーダンスZoは次の式で与えられます。
(差動出力のときの1/2です)
Zo = Rc
よって今回の実験回路では
Rc = 4.7[kΩ]
-
差動増幅の場合、トランジスタの入力インピーダンスは一律に決まらないと思われます。
が最大でも
Zb(max) = 2 * hie
です。β=180(=hfe)とし、概算式 hie = β/(40 * Ic)を使い
Zb(max) = 2 * β/(40 * Ic) = 2 * 180/(40 * 1.1[mA] ≒ 8182[Ω]
これと、RB1(=RB2)が並列となるので
Zi(max) = RB1 // Zb(max) = 100[kΩ] // 8182[Ω] ≒ 7563[Ω]
形成します。
そのカットオフ周波数をfciとすれば、
fci = 1/{2π * Ci * (Rs + Zi)}
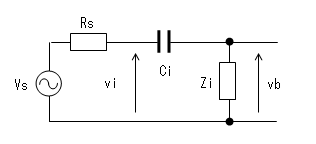
Ziは入力インピーダンスの項で計算しました。
設計条件よりRs=600[Ω]になります。
(Rsが不明の場合はワースト・ケースとしてRs=0と考えて計算してもよいでしょう。)
信号の最低周波数をfsとすれば
fs >> fci
となるようにCiを決定すればよいことになります。よって
fs >> 1/{2π * Ci * (Rs + Zi(max))}
∴Ci >> 1/{2π * fs * (Rs + Zi(max))}
設計条件より入力信号の最低周波数(fsl)を50[Hz]とします。
Ci >> 1/{2π * 50 * (600 + 8182)} ≒ 0.36[μF]
となりかなり小さな値ですみます。今回は Ci1 = Ci2 = 10[μF]としました。
ローカット・フィルターを構成します。カットオフ周波数(fco)は
fco = 1/{2 * π * Co * (Zo + ZL)}
となります。
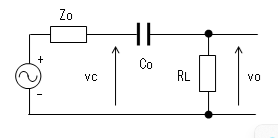
信号の最低周波数をfsとすれば
fs >> fco
となるようにCoを決定すればよいことになります。よって
fs >> 1/{2π * Co * (Zo + RL)}
∴Co >> 1/{2π * fsl * (Zo + RL)}
まず、出力インピーダンスの項で計算した結果からZoは
Zo ≒ 4700[Ω]
設計条件よりRL = 1[MΩ]、
入力信号の最低周波数(fsl)を50[Hz]とします。
Co >> 1/{2π * 50 * (1[MΩ] + 10[kΩ])} ≒ 0.003[μF]
となり小さな値ですみます。
今回は手持ちのコンデンサーの関係で Co1 = Co2 = 22[μF]としました。
実験方法
-
信号源としては、低周波発振器
を使用します。
周波数は1kHzとしました。
出力レベルは発振器で調整します。
発振器の出力インピーダンスは約600[Ω]です。
- 電子ブロックの配置 電子ブロックで実験回路を下図のように組み立てます。
- 直流動作点の測定
電子ブロックで回路を組み立てたら電源VCC(10V)と電源電圧VEE(6V)を 接続します。
ディジタルテスターの直流電圧測定レンジで、下図に示すように VC1、VC2、VE、
VB1、VB2を測定します。 IC1はVC1とRC1の値から IC1=VC1/RC1の式により求めます。
また、IC2もVC2とRC2の値から IC2=VC2/RC2の式により求めます。
また、電源電圧VCCと電源電圧VEEも正確に10.0[V]と6.0[V]ではないので、
測定しておきます。
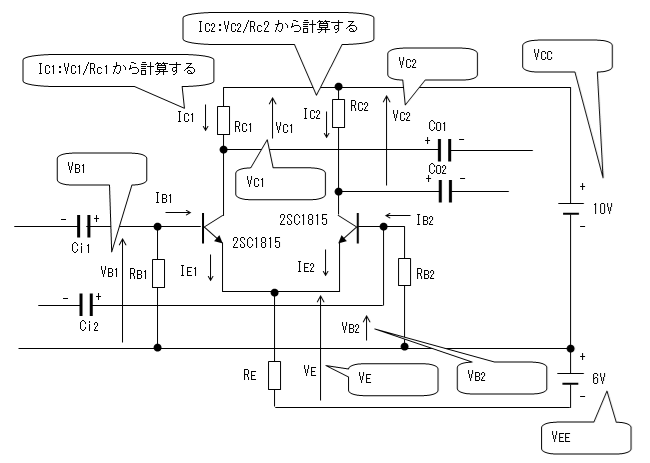
- 増幅波形の観測・増幅度の測定
以下の手順において交流電圧計とは、 テスターアダプタ+ アナログ直流電圧計 のことです。
(1)vi1に低周波発振器(1k[Hz])を接続します。
(2)vi2はグランド(GND)に接続します。【必須】
(3)交流電圧計でvi1を測定し、低周波発振器の出力を10[mV]に設定します。
(20[mV]にすると、出力が多少歪むようです)
(4)交流電圧計でvo1を測定し、オシロスコープで波形を観測します。
(5)交流電圧計でvo2を測定し、オシロスコープで波形を観測します。
(6)vi1の低周波発振器とvi2のグランド接続を外します。
(7)vi2に低周波発振器(1k[Hz])を接続します。
(8)vi1はグランド(GND)に接続します。【必須】
(9)交流電圧計でvi2を測定し、低周波発振器の出力を10[mV]に設定します。
(20[mV]にすると、出力が多少歪むようです)
(10)交流電圧計でvo1を測定し、オシロスコープで波形を観測します。
(11)交流電圧計でvo2を測定し、オシロスコープで波形を観測します。
(12)vi1のグランド接続とvi2の低周波発振器を外します。
- 同相増幅の波形観測・同相利得の測定
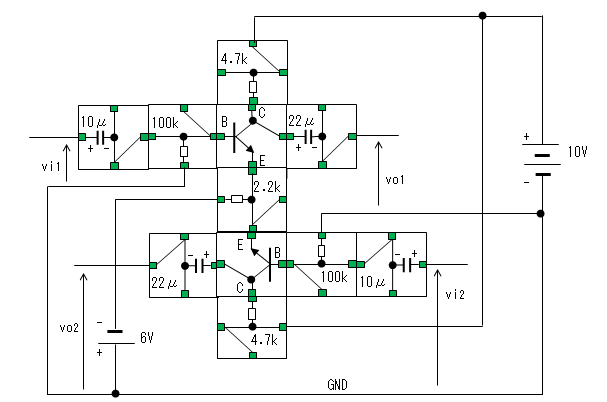
(1)vi1とvi2に低周波発振器(1k[Hz])を接続します。
(2)交流電圧計でvi1(またはvi2)を測定し、 低周波発振器の出力を20[mV]に設定します。
(3)交流電圧計でvo1を測定し、オシロスコープで波形を観測します。
(4)交流電圧計でvo2を測定し、オシロスコープで波形を観測します。
実験機材
- 電子ブロック
- 低周波発振器
- テスターアダプタ
- アナログ直流電圧計
- 簡易安定化電源 (10[V]端子)
- 乾電池:1.5[V]×4
- ディジタル・テスター
- オシロスコープ
-
トランジスタ(2SC1815)×2
抵抗器:2.2k、4.7k×2、100k×2
電解コンデンサ:22μF×2、10μF×2
実験結果
- 直流動作点 下図にに測定結果を示します。
- 波形観測
- 電圧増幅度
- CMRR 今回は逆相の入力を用意出来なかったので(差動増幅回路をもう1回路用意
白色の吹き出しが設計値(理論値)、黄色の吹き出しが測定値です。
Ic2がやや計算値より小さいですが、トランジスタのバラツキ
によるものと推定します。他は概ね設計値に近いと考えます。
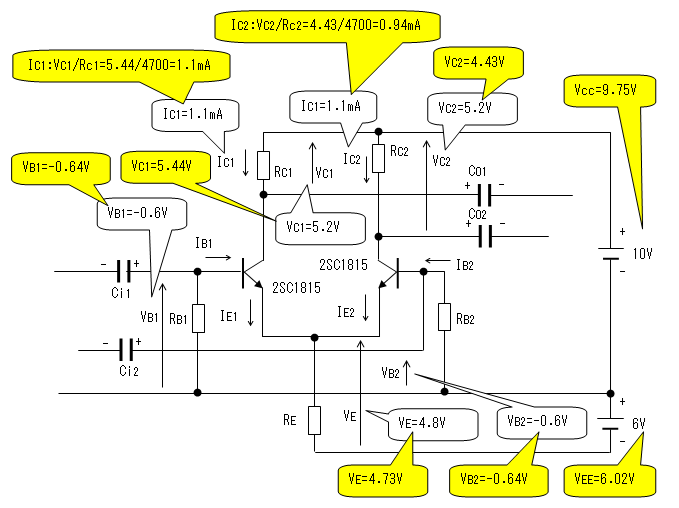
| vi1入力 電圧 |
vi2入力 電圧 |
出力(vo1)波形 | 出力(vo2波形) | 備考 |
| 20[mV] | 0[mV] |
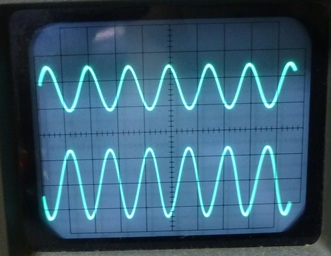 上:vi1、5mV/div、0.5ms/div 下:vo1、1V/div、0.5ms/div |
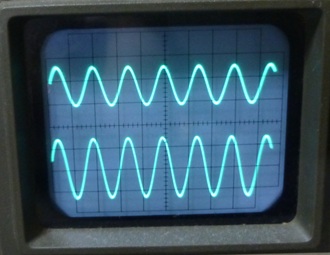 上:vi1、5mV/div、0.5ms/div 下:vo2、1V/div、0.5ms/div |
|
| 0[mV] | 20[mV] |
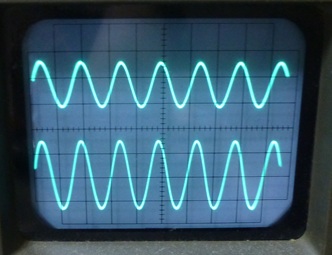 上:vi2、5mV/div、0.5ms/div 下:vo1、1V/div、0.5ms/div |
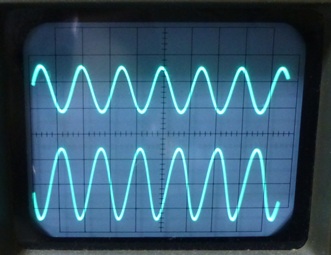 上:vi2、5mV/div、0.5ms/div 下:vo2、1V/div、0.5ms/div |
|
| 20[mV] | 20[mV] |
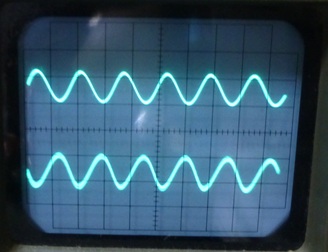 上:vi1、50mV/div、0.5ms/div 下:vo1、50mV/div、0.5ms/div |
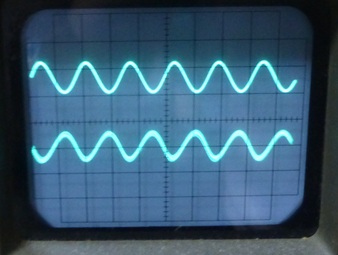 上:vi2、50mV/div、0.5ms/div 下:vo2、50mV/div、0.5ms/div |
同相入力 |
| 入力[mV] | 出力 | 増幅度 | 備考 | |||||
| vi1 | vi2 | vo1 | vo2 | vo1実測値 | vo2実測値 | 理論値(絶対値) | 偏差 | |
| 10 | 0 | -0.96[V] | 0.96[V] | vo1/vi1 = -96 | vo2/vi1 = 96 | 103 | -6.8[%] | |
| 0 | 10 | 1.00[V] | -1.00[V] | vo1/vi2 = 100 | vo2/vi2 = -100 | 103 | -2.9[%] | |
| 20 | 20 | -24[mV] | 20[mV] | vo1/vi1 = 1.2 | vo2/vi2 = 1.0 | 1.068 | 12[%]/-6.4[%] | 同相入力 |
すれば良かったのですが。笑)、vi1またはvi2のみ入力したときの
利得(増幅度)で計算します。この値は差動利得Adの1/2です。
そして、vi1のみ入力したときの利得(増幅度)は96で、
vi2のみ入力したときの利得(増幅度)は100なので、とりあえず(?)
平均すると98です。一方実験から得られた同相利得(Ac)の値も1.2と1.0なので、
これも平均をとると1.1となるので、実験結果からCMRRを求めると
CMRR = |Ad| / |Ac| = (2 * 98) / 1.1 ≒ 178.2
| CMRR実測値 | CMRR理論値 | 偏差 |
| 178.2 | 193.6 | -8.0[%] |
測定結果・考察
- 直流動作点 今回使用したトランジスタは同一ロットではないことから、hパラメータが異なる
- 波形観測 (1)vi1に対し、vo1は逆位相、vo2は同位相となりました。
- 電圧増幅度 (1)差動利得
- CMRR 実測値と理論値とで8[%]の偏差がありましたが、トランジスタのバラツキなどで
と考えられ、多少バランスが悪くなりました
トランジスタに同一ロットのものを使用したり、デュアルトランジスタを
使用すればバランスは改善すると期待されます。
(2)vi2に対し、vo1は同位相、vo2は逆位相となりました。
(3)同相入力に対しては理論値とほぼ一致する出力が発生しました。(次項参照)
実測値と理論値とで約7[%]の偏差がありましたが、トランジスタのバラツキなどで
この程度の偏差はやむなしと考えます。よって、実測値と理論値は概ね一致している
と判断します。
(2)同相利得
理想的な差動増幅では同相入力に対して出力は0ですが、今回の実験回路は
理想的でないため、出力が発生しました。
実測値と理論値とで約12[%]の偏差がありましたが、トランジスタのバラツキなどで
この程度の偏差はやむなしと考えます。よって、実測値と理論値は概ね一致している
と判断します。
この程度の偏差はやむなしと考えます。よって、実測値と理論値は概ね一致している
と判断します。
今後の課題
- REを定電流源に置換えて、今回の実験結果と比較する。
参考文献
- 2SC1815データシート
関連項目
- トランジスタ増幅回路の解析−差動増幅回路の解析
- 電子回路−バイポーラトランジスタの等価回路
- 電子回路−トランジスタのhパラメータ
- 抵抗器に関する情報−E6系列
- 自作電子ブロック
- 低周波発振器
- 簡易安定化電源
- テスターアダプタ
- アナログ直流電圧計