概要
抵抗値、静電容量(キャパシタンス)、インダクタンスを測定するためのブリッジです。抵抗測定の原理はホイートストン・ブリッジです。
静電容量(キャパシタンス)の測定には交流ブリッジの一種である ソーティの容量ブリッジを
またインダクタンスの測定にはマクスウェル・ブリッシを 使用しています。
回路図はネットから拾ってきたものを一部定数を変更しました。
(オリジナルはどこだったか判らなくなりました。)
本製作においては更に周波数ブリッジ を使った正弦周波数の測定機能も追加しました。
仕様
- 抵抗[R]、キャパシタンス[C]、インダクタンス[L]の測定範囲とレンジ

- 周波数(F)
- 約34Hz 〜
(上限?)500Hz (*1)
正弦波に限ります。(波形が歪んでいると平衡しません。)
(*1)誤差20%を許容すると、〜1kHz
- 約34Hz 〜
外観

回路図

回路構成
- 抵抗(R)
-
抵抗測定の原理はホイートストン・ブリッジ
です。
- コンデンサ(C)
-
静電容量(キャパシタンス)の測定には交流ブリッジの一種である
ソーティの容量ブリッジを 使用します。
- コイル(L)
-
インダクタンス測定には
マクスウェル・ブリッシを使用しています。
- 周波数(F)の測定範囲
-
周波数測定には周波数ブリッジ
の一種であるウィーン・ブリッジを使用します。
設計
ほとんど原理図に近いので、とくに設計はしていないのですが(笑)以下にレンジ毎の測定範囲の計算を示します。
- 抵抗測定(ホイートストン・ブリッジ)

ホイートストン・ブリッジの原理より
X = RB/Q
S = 1kΩ、B = 47〜1047Ωであることから
- レンジ1(1〜10Ω) R = 10Ω X = 0.47〜10.47Ω
- レンジ2(10〜100Ω) R = 100Ω X = 4.7〜104.7Ω
- レンジ3(100〜1kΩ) R = 1kΩ X = 47〜1047Ω
- レンジ4(1k〜10kΩ) R = 10kΩ X = 470〜10.47kΩ
- レンジ5(10k〜100kΩ) R = 100kΩ X = 4.7k〜104.7kΩ
- レンジ6(100k〜1MΩ) R = 1MΩ X = 47k〜1047kΩ
- レンジ1(1〜10Ω) R = 10Ω X = 0.47〜10.47Ω
- キャパシタンス測定(ソーティの容量ブリッジ)

ソーティ・ブリッジの原理より
Cx = B/R・Cs
Cs = 0.01μF、B = 47〜1047Ωであることから
- レンジ1(0.1〜1μF) R = 10Ω Cx = 0.047〜1.047μF
- レンジ2(0.01〜0.1μF) R = 100Ω Cx = 0.0047〜0.1047μF
- レンジ3(0.001〜0.01μF) R = 1kΩ Cx = 470p〜0.01047μF
- レンジ4(100p〜1000pF) R = 10kΩ Cx = 47p〜1047pF
- レンジ5(10p〜100pF) R = 100kΩ Cx = 4.7p〜104.7pF
- レンジ6(1p〜10F) R = 1MΩ Cx = 0.47p〜10.47pF
- レンジ1(0.1〜1μF) R = 10Ω Cx = 0.047〜1.047μF
- インダクタンス測定(マクスウェル・ブリッシ)

マクスウェル・ブリッジの原理より
Lx = RB・Cq
Cq = 1000pF、B = 47〜1047Ωであることから
- レンジ1(1〜10μH) R = 10Ω Lx = 0.47〜10.47μF
- レンジ2(10〜100μH) R = 100Ω Lx = 0.47〜10.47μF
- レンジ3(100μ〜1mH) R = 1kΩ Lx = 0.47〜10.47μF
- レンジ4(1m〜10mH) R = 10kΩ Lx = 0.47〜10.47μF
- レンジ5(10m〜100mH) R = 100kΩ Lx = 0.47〜10.47μF
- レンジ6(100m〜1H) R = 1MΩ Lx = 0.47〜10.47μF
- レンジ3(100μ〜1mH) R = 1kΩ Lx = 0.47〜10.47μF
- レンジ1(1〜10μH) R = 10Ω Lx = 0.47〜10.47μF
- 周波数測定(ウィーン・ブリッジ)

ウィーン・ブリッジの原理より
f = 1/(2πC・F)
C = 4.7μF、F = 0〜1000Ωであることから
- f = 約34Hz〜(上限?)
- f = 約34Hz〜(上限?)
使用部品
- 固定抵抗器
47Ω以外は出来るだけ精密な金属皮膜抵抗器を使用します。
- 固定コンデンサ
出来るだけ精密で経年変化の少ないコンデンサを使用します。
容量の観点からフィルム系のコンデンサを使用しました。
- 可変抵抗器
機械構造の安定したものが望まれます。通信工業規格品を使用しました。
カーブは全てBカーブです。
製作
- ケース
タカチのYM-180を使用しました。
- 寸法

- 刻印文字

使用方法
- レンジの設定によるRの値
以下の測定手順において、抵抗値Rの値はレンジの設定(1〜6)により以下の値を使用します。

- 電気抵抗(R)測定(直流ブリッジによる方法)
- 接続方法

- 測定手順
(1)ブリッジの機能設定で「R」を選択します。トグルスイッチはTと反対側(M)にします。
(2)センターメータに感度設定がある場合「低感度」に設定します。
(3)回路を組立ます。乾電池は最後に接続します。
(4)被測定抵抗器を接続します。
(5)レンジのスイッチとBALANCEのVRを交互に調整してセンターメーター の指示が0になる設定を探します。
(6)センターメーターに感度設定があれば「高感度」に設定します。
(7)BALANCEのVRを調整してセンターメーターの指示を0にします。
(8)センターメータに感度設定がある場合「低感度」に設定します。
(次の(9)でバランスがくずれメーターが振り切れるからです。)
(9)ブリッジのトグルスイッチをT側に倒します。
(10)その時の抵抗値を読み取ります。(この値をBとします)
(11)以下の計算式により、測定値Xを求めます。Sは1kΩです。
X = R*B/S
Rはレンジの設定によります。1項を参照してください。
(12)被測定抵抗を交換する場合は、ブリッジのトグルスイッチをTと反対側(M)倒し
(5)〜(11)の手順を繰り返します。
- 接続方法
- 電気抵抗(R)測定(交流ブリッジによる方法)
- 接続方法

- 測定手順
(1)ブリッジの機能設定で「R」を選択します。トグルスイッチはTと反対側(M)にします。
(2)発振器の出力を最小にします。
(3)回路を組立ます。発振器の電源は最後にONにします。。
(4)被測定抵抗器を接続します。
(5)発振器の出力を適当な音量になるまで上げます。
(6)レンジのスイッチとBALANCEのVRを交互に調整して音が消える点を探します。
(7)音が小さくなったら発振器の出力を上げます。
(8)BALANCEのVRを調整して音が消える範囲の中央に設定します。
(9)発振器の出力を最小にします。
(次の(10)でバランスがくずれイヤホンから大きな音が出るからです。)
(10)ブリッジのトグルスイッチをT側に倒します。
(11)その時の抵抗値を読み取ります。(この値をBとします)
(12)以下の計算式により、測定値Xを求めます。Sは1kΩです。
X = R*B/S
Rはレンジの設定によります。1項を参照してください。
(13)被測定抵抗を交換する場合は、ブリッジのトグルスイッチをTと反対側(M)倒し
(5)〜(12)の手順を繰り返します。
- 接続方法
- キャパシタンス(C)測定
- 接続方法

- 測定手順
(1)ブリッジの機能設定で「C」を選択します。トグルスイッチはTと反対側(M)にします。
また、可変抵抗の「D/F」は最小に設定します。
(2)発振器の出力を最小にします。
(3)回路を組立ます。発振器の電源は最後にONにします。
(4)被測定インダクターを接続します。
(5)発振器の出力を適当な音量になるまで上げます。
(6)レンジのスイッチとBALANCEのVR、可変抵抗D/Fをそれぞれを調整して
音が消える点を探します。
(7)音が小さくなったら発振器の出力を上げます。
(8)BALANCEのVRと可変抵抗D/Fを調整してBALANCEのVRを音が消える範囲の中央に設定します。
(9)発振器の出力を最小にします。
(次の(10)でバランスがくずれイヤホンから大きな音が出るからです。)
(10)ブリッジのトグルスイッチをT側に倒します。
(11)その時の抵抗値を読み取ります。(この値をBとします)
(12)以下の計算式により、測定値Xを求めます。Csは0.01μFです。
Cx = B/R・Cs
Rはレンジの設定によります。1項を参照してください。
(13)被測定抵抗を交換する場合は、ブリッジのトグルスイッチをTと反対側(M)倒し
(5)〜(12)の手順を繰り返します。
(14)測定容量がpFオーダーのときは浮遊容量の値を測定値から引きます。
浮遊容量は、測定端子Xに何も接続しない状態で容量を測定します。
本製作においては20〜25pF程度の浮遊容量がありました。
- 接続方法
- インダクタンス(L)測定
- 接続方法

- 測定手順
(1)ブリッジの機能設定で「L」を選択します。トグルスイッチはTと反対側(M)にします。
また、可変抵抗の「Q」は最大に設定します。
(2)発振器の出力を最小にします。
(3)回路を組立ます。発振器の電源は最後にONにします。
(4)被測定インダクターを接続します。
(5)発振器の出力を適当な音量になるまで上げます。
(6)レンジのスイッチとBALANCEのVR、可変抵抗Qをそれぞれを調整して
音が消える点を探します。
(7)音が小さくなったら発振器の出力を上げます。
(8)BALANCEのVRと可変抵抗Qを調整してBALANCEのVRを音が消える範囲の中央に設定します。
(9)発振器の出力を最小にします。
(次の(10)でバランスがくずれイヤホンから大きな音が出るからです。)
(10)ブリッジのトグルスイッチをT側に倒します。
(11)その時の抵抗値を読み取ります。(この値をBとします)
(12)以下の計算式により、測定値Xを求めます。Cqは1000pFです。
Lx = R*B・Cq
Rはレンジの設定によります。1項を参照してください。
(13)被測定抵抗を交換する場合は、ブリッジのトグルスイッチをTと反対側(M)倒し
(5)〜(12)の手順を繰り返します。
- 接続方法
- 周波数(F)測定
- 接続方法
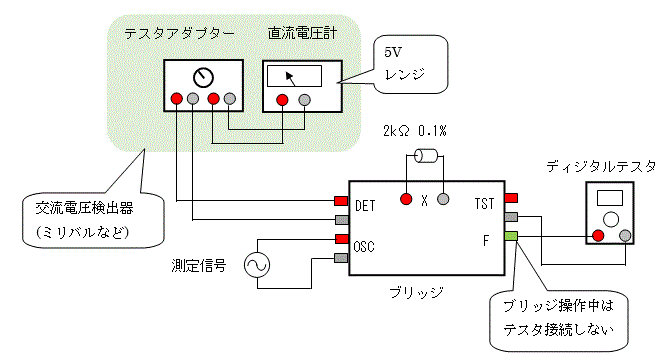
- 測定手順
(1)回路を組立ます。このとき測定に影響しないよう、テスターは接続しません。
(2)被測定端子には2kΩの精密抵抗器を接続します。
(3)ブリッジの機能設定で「F」(周波数測定)を選択します。
(4)ブリッジのRANGEは「3」に設定します。
(5)測定信号源の出力を最小にして接続(または電源ON)します。
(6)検出器のメータが適度に振れる位置まで測定信号の出力を上げます。
(7)D/FのVRを調整して検出器のメータが最小になる点を探します。
(8)検出器のメータの振れが大きくなるよう5kΩVRの出力を上げます。
(9)7〜8を繰り返して検出器の振れが最小になるD/FのVRの設定点を見つけます。
(10)テスターの読み取りに影響しないよう、測定信号の出力を0にします。
(11)テスターをF端子とDET端子のマイナス側(黒ターミナル)間に接続します。
(12)その時の抵抗値を読み取ります。(数回測定し、平均値をFとします)
(13)以下の計算式により、測定周波数f[Hz]を求めます。Cは4.7μFです。
f = 1/(2*π*C*F)
【重要】周波数ブリッジでは信号源の高調波により、平衡点が判りづらいことがあります。
とくに検出器がイヤホンの場合、ほとんど分からないことがありました。
その場合は、検出器としてミリバルやアナログ電圧計またはオシロスコープなどを
使用すると良いです。
関連項目
参考文献
- 入門電気計測(第16刷 1980)、西野治著、実教出版
- 電気工学入門演習 電気計測(3版 1988)、堤捨男・金古喜代治 共著、学献社